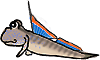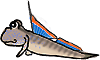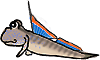セプテムラディアトゥス飼育記
ペリオプタルモドン・セプテムラディアトゥス
ショップインボイスはベトナムマッドスキッパー
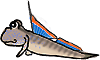

Vietnam mudskipper/鱗峽齒彈塗魚
セプテムラディアトゥス
| 和名 |
なし |
| 通称 |
ベトナムマッドスキッパー(ショップによるインボイス) |
| 学名 |
Periophthalmodon septemradiatus |
| 読み |
ペリオプタルモドン セプテムラディアトゥス |
| 寿命 |
自然下で恐らく3年程度。飼育下で4〜5年と思われる
|
| 体長 |
最大で10cm前後 |
| 分布 |
マレーシア、インド、ミャンマー、タイ、ベトナム等に分布 |
| 生息域 |
河口の干潟(汽水域) |
| 食性 |
干潟の小さいカニやヨコエビなどの甲殻類、多毛類、虫など |
| 雌雄差 |
雄は成長に従い第一背鰭が大きくなり第一棘条が伸長する |
| 産卵期 |
4~9月、詳細は知られていないらしい。泥中の巣穴は50cm以上、時にメートル級に達し、横穴を作って産卵室を設ける。 |
| 冬期 |
自然下では越冬用の巣穴を掘り、代謝を落とし休眠に近い状態になる。
飼育下では通年活動する |
呼吸
※属共通 |
水中で鰓を使って呼吸する以外に、皮膚をぬらした状態を保つことで、ある程度の皮膚呼吸ができる。また、口中に水を貯め、鰓へ送る事で陸上でもしばらくの間、鰓呼吸が可能。 |
セプテムラディアトゥスは魚食性の高いオオトビハゼの仲間で、Periophthal
modon(ペリオプタル
モドン)属になる。
オオトビハゼ属は幼魚の間、第一背鰭が極端に小さいという共通の特徴を持っている。また、雌は成魚になっても第一背鰭が殆ど成長しない。
熱帯魚ショップのインボイス(販売者や流通業者がつけた通称)はベトナムマッドスキッパーである事が多い。ベトナム便で入荷した事からつけられた通称だが、そのため同じベトナム便で輸入される別種のマッドスキッパーに対しても同じ通称を使う可能性はある。飼おうとする人はショップ表記の名前に頼らず、よく見て判断したほうがいい。
飼育環境の補足
飼育の詳細は
アクアリストのためのマッドスキッパー飼育方法を参照
この種の魚にしては相当な淡水域まで進出するという(さりとて汽水魚には違いない)。そこから考えると海水の17~20%程度の薄い濃度の汽水を使用するのがいいのではないかと思う。海水の17~20%の濃度にするには、市販の「海水の素」に書いてある規定量の6分の1~5分の1を溶かせばいい。
誰なんだチビスキッパー 成長記
チビよ、食え、太れ、そして育て! 2003.01.13飼育開始

(文中の「○」には「水」が入ります)
お店にマッドスキッパーがいる、しかも「純淡○産と聞いた」と掲示板で教わった。その翌日、さっそくその店に見に出かけた。青っぽい魚体だという話だ。
情報いただいた通り、居た。確かに純淡○産と書かれて。
お店にその理由を尋ねると、仕入れ元からそう聞いたから書いたと返答。そりゃそうだね…未知種の場合、 小売り店さんは仕入れ元からの情報を信じるしかないから。仕入れ元>現地の販売業者>個別の取り子さんが川で捕ったと言った事をうけて伝えた。それならそう言われても仕方ない。

でも川で採れる魚は全て淡○魚だと言えないのは、魚好きならご存じの事。とはいえ世の中広いので マッドスキッパーに純淡○種は居ない!とは言えない。いや、居たらいいなあと思います。

ただ、そうでない(汽水種である)可能性のほうが高いので、いくら張り紙に「純淡○産」と書いてあろうとも、判断するのはこちらの役目…そこで、私の新しいマッドスキッパーは17.5%海水(やや薄い汽水)で飼う事に決めました。
最初の経過報告日誌 2003.1.11~5.11
1月13日 ショップで対面した当日
予想はしていたが、やっぱり激ヤセ個体だ。
見たところ半数は陸に上がれてない。店に聞いたところによると餌は何でも食べているとの事なんだが。。餌を食べつつも痩せたままというのは、生命維持活動による消耗が激しいと考えるべきかと。

1月15日 買い残した個体が淡○に浸かっていると思うと気になって吐きそうなので、 残り2匹を買いに走る。このマッドスキッパーは縄張りが広く闘争が激しいようだ。
1月21日 最も変な痩せ方をしていた個体1匹死亡
1月22日 最も飯を食わなかった個体が元気に採餌。
1月26日 最小の個体は殆ど陸に上がらない。餌は少し食う。
1月27日 ちょっと太ったような。そして記念撮影(下写真)

と、ここまでの間、種類が判りかねていたのだが
どうやらマッドスキッパー既知種中ではPeriophthalmodon septemradiatusで間違いなさそう。
2003.1.28 最初は皮膚と背鰭見てオオトビハゼ属だと思ったものの、念のためアフリカンの稚魚の可能性も検討。
でも見ればみるほど普段の模様が違うし。それにこの目を貫く感じの黒いストライプ、小さすぎる背鰭で決定的。そこで恐らく、オオトビハゼ属の既知種で最も小型のセプテムラディアトゥスで正解だろうと考えた。後にトビハゼ属を研究をしている人の意見も私と同じと判り、彼らをセプテムと呼ぶようになった。
2003.5.11追記 ベトナム便が定期的に入るようになったらしく、ショップにかなり出回りはじめた。飼育する人もそこそこ増えてきた。


その後のセプテム達
小型の割りに獰猛な彼らが同じ水槽で3匹一緒に暮らすようになるまでの経過です。
◆1つの水槽をセパレーターで3つに分け個室にして観察。
↓
◆セパレーターを器用に潜り抜けて隣の仕切り内に入るので、諦めてセパレーターを外して3匹一緒にし、注意して観察。
↓
◆ちょっとした追い立てが時折見られる。1匹がとても小さく、他の2匹を恐れて岩の下から出てこない。そこで水中に餌を投入しながら約1週間ほど様子を見る。
↓
◆餌は食べているが、どうしても恐れて陸に上がれない様子なので、結局、3匹別々の小型水槽に分ける。これで3ヶ月過ごす
↓
◆体格が近い2匹を同じ水槽にして様子を見る。ミナミトビハゼのような過激な争いは見られない。餌も問題なく2匹に与えることができる。お互いが近くにいても気にならない様子。この状態を約半年継続
↓
◆1匹にしたほうは相変わらず臆病だが陸にも上がるようになり、餌も食べて順調に体格が向上。
↓
◆万全を期して3匹がほぼ同じ大きさになるまで待ち、体格が揃ったところで水槽を1サイズ大きくし、広い陸地を作って3匹を1つの水槽に入れた。以降、闘争も殆どない暮らしが続く。
体格とパワーがほぼ均一になった瞬間があったからこその同居成功なので、日々状態をよく観察して、強弱が出てきたと思ったら迷わず1匹づつに分けようと思う


雄の背鰭は何度か見たが、なかなか撮らせてくれない
背びれを閉じていても色は少しわかる。彼らの背鰭は第一・第二ともに赤青ツートンで、とても綺麗なもの。でも滅多に見られない。1年たつが、餌やりのときに張り合う程度で、今のところケンカをしないため。
(これで大人しいなんて思ってはいけない。魚を食べることと同種の同体格の魚を攻撃しないのは別問題)
体も胸鰭もなかなか綺麗。胸鰭は多色に光っているのがわかる。
写真はオス、一番からだが大きかった個体

第一背鰭はいつ生えるかな(1年経過しても生えない個体)
(仮に彼女と呼ぶ)この白っぽい魚は普段はもう少し色濃いこともある。
最初家に来たときからずっと気になっていることが1つ。彼女には背鰭1がない。(恐らく成長しても背鰭1が極端に小さいということで、だから多分メスだと思う)
なにせペリオプタルモドンなので、他の個体と同じように、そのうち背中に小さい三角が出てきて、じきに大きな背鰭になるだろうと思っていた。他の個体が3ヶ月程度で小さな三角から立派な背鰭になったにもかかわらず、彼女は1年たった今も、まだ第一背鰭が生える気配すらない。面白いものだ。まだまだ観察していこう。別種の可能性も一応念頭に置いて。
(その後の追記:やはり雌だった)

魚食魚なんだけど、普通にミミズやアカムシを食べる
この個体は大量のアカムシをくわえたまま逃げてたやつ。それを見ていたもう1匹は、追うでもないがじっとにらみ据えていた。じきにイラついてきた(と私には見えた)のか、睨んだまま胸鰭をしきりとパタパタさせていた。
めだかなど入れてやれば追って食べるだろうが、小型種だけにアカムシも大いに食べてくれるので特に活餌を与える予定はない。それでもたまに釣り餌のゴカイが余れば与えるし、生き生きと狩って食べてくれる。
他にも、冷凍ブラインシュリンプも食べるし乾燥クリルも食べるが、やはりアカムシ一番人気。

どうにかこうにか、背鰭を撮ってみた
陸上での争いがめったにないのは良いことだ。だがそのせいで背鰭の写真の撮影チャンスがなくて困っていた。どうしても撮りたいので、多少暗いが水中に降りたところでパシャッと撮影。シャッタースピードが遅いのでどうしてもブレがきてしまうものの、大体の形と色がわかる写真が撮れた
胸鰭にも綺麗なメタリックブルーを中心とした数色の斑点模様が見られる。
それにしても、あの激ヤセが嘘のように立派になった。やっぱりペリオプタルモドンも汽水で飼うのがベストのようだ
2011年末に思い立ってサイトデザインだけ更新をかけていて、
2006年に撮影した写真が出てきたので、日付を見ながら当時のことを思い出した。
セプテムラディアトゥスは2006年9月に最後の1匹が死んだ。
飼育期間は2003年1月から数えて3年8ヶ月。
とても綺麗な魚体を庭に埋めながら、またしても目が溶けるほど泣いたんだった。
最期の写真を見たけど、第一背鰭の軟条が上の写真よりもっともっと長くなっていた。