| 水環境 (詳細説明) |
汽水濃度 20~25%海水 |
| 水温 24~26度 (最高水温30度程度) | |
| 水質 弱アルカリ(7.5~8) | |
| 水深 体長と同じ~体高の半分強が浸る程度 | |
| エアレーション:弱くかける。 | |
| ろ過装置:不要 | |
| 陸環境 (詳細説明) |
なめらかで登りやすいもの なおかつ乗ってぐらつかない・浮かないもの(浮島ダメ) |
| 照明 (詳細説明) |
通常の、熱帯魚用のもの |
| 餌 (詳細説明) |
クリル、カーニバル、冷凍アカムシ等の肉食魚用飼料やフレーク餌を陸に置いて与えるが、どうしても陸に上がらない個体には、隠れ場所あたりに沈めて落とす。 手に入るなら小型のカニやゴカイ類、口に入るサイズの活きた小魚やエビを与えても良い。 ※大型のオオトビハゼ属の場合、小赤やメダカ等の活き餌が必要な場合もある |
| 汽水濃度 20~25%海水 |
海水を100%として、20~25%の塩分に調節。 ※カルキ抜きは通常通り行ってください。 <例> 粉タイプの海水の素が1リットルあたり40グラムの場合、 汽水では1リットルあたり8~10グラムを使用する。 |
| 水温 26度前後 |
一部の種を除き、主な種が亜熱帯に生息しているため、種類が判然としない場合はヒーターを入れて飼育するのが安全。冷水種は存在しないので、ヒーターが原因で体調を崩すという事はない。 飼育する魚の詳細な種類が判る場合にのみ以下を参照。 日本産で、関東にも生息する「トビハゼ(※固有の名称。総称ではない)」であれば、10度~30度程度の範囲で飼育可能。 |
| 水質 弱アルカリ (Ph7.5~8) |
それほど細かに気にする必要はないが、 主な生活域が汽水域である事を考慮し、弱アルカリを心がける。 |
| 水深 体長と同じ(推奨)~ 体高の半分強 |
水中での鰓呼吸もしますが、口にふくんだ水を鰓に送る事によって陸上で鰓呼吸をしたり、濡れたヒフからヒフ呼吸します。 また、自然の状態では水深の深い場所に沈んだまま生活する事はないため、このような水深での飼育となります。 <例> アフリカンマッドスキッパー成魚の例 体長20cm、体高3cm: 水深2cm~20cm ミナミトビハゼ成魚の例 体長10cm、体高2cm: 水深1.5cm~10cm 体長と同じ程度の水深(安全水位) 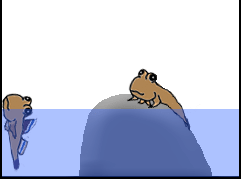 ■例写真> 写真1 ※ヒーターは通常の水中用を使用。ヒーターカバーをつけて底に寝かせて設置。 体高の半分程度の水深(要注意水位) 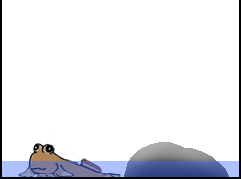 ■例写真> 写真1・写真2 ※ヒーターはシート型ヒーター(水槽外に設置)になる。 極小の幼魚でも水深1cmは確保必須。 水深が浅い場合に起きる問題: 温度が一定に保ちづらい、水質の悪化が早い、蒸発が早く濃度が濃くなるため頻繁に足し水が必要、などの問題から、小サイズ水槽での極浅仕様は勧められない。 |
| エアレーション:弱くする。 | エアレーションの目的は水を静かに動かして、澱ませず水を腐らせない事にあります。水中に酸素を多量に含ませる事が目的ではありません。 ■強いエアレーションは強い水流を起こします。 彼らは長時間遊泳する事に向いていないため、常に強い水流があると負担になりますし、 水流の強さによっては溺れます。 当然、水流が起きるようなろ過装置も使用不可 |
| ろ過装置:基本的に不要 ※低水量の場合。大型水槽はこの限りではありません。 |
水量が極端に少ないため、水は汚れやすく、また頻繁な足し水が必要なため、ろ過を完成させる事は大変難しいと考えられます。 汽水のろ過に非常に詳しく、自信がある、という方は別として、水換え頻度の軽減を目的としたろ過装置の設置はあまり意味を成さないと思います。 ろ過ではなく水換えによって水質を保ちます。 ■水作やロカボーイ等は「投げ込み式ろ過装置」としてでなく、水が腐らないように軽く循環させるために使っています。水深が浅い場合に陸地がわりにチョイとすわれて、エントツ部分が水から突き出ているから飛沫が飛んで体も濡れるし便利だね、程度にお考え下さい。 ※うちだけ読んで、表現をまるごと真似て書かれてしまった場合、その人に恥をかかせてしまう可能性があるので一言。あの部分をエントツと呼ぶのは一般的な表現ではないですよ。 |
| メンテナンス |
■淡水の足し水はマメにする。水量が少ないため、蒸発すると汽水の濃度があがってしまいます。最初の水位に目印をしておき、減ってきたら淡水を水位まで足し水します。 ■半月に1度は半量~全量の水換え。水量が少ないこともあり生物ろ過は期待できないためアンモニア濃度があがりやすい。※低水量の場合。大型水槽(90cm以上)はレイアウトによってはこの限りではありません。 |
| なめらかで 登りやすく ぐらつかず 浮かないもの ※更に詳しくは、 次ページに続く「陸地のタイプと良い点・悪い点」等を参照。 |
石、流木、陶器などの人工物、特に材質は選びませんが、条件として ・水質を激変させない事 ■強い酸性に傾いたり、塩分によって有害な物質が溶け出さないものを選んでください。 ■どれが良いかわからない場合は 砂岩・素焼きの鉢・マングローブ流木(なめらかな肌のもの)などをお選び下さい。 ・尖ったりギザギザがなく、なめらかな質感のものである事。 ■直接這って登ったり、他所から飛び乗ったりするのでケガの危険がある ワンポイントアドバイス 尾または体の下部だけ水に浸せるような陸地と、全身が水から出せる場所の両方があると より良いです。 |
| 通常の、熱帯魚用のもの | 陸地にいる事が多いため、カメなどのは虫類と飼育方法を混同してしまう方がありますが、 あくまで魚ですので、普通の熱帯魚用のライトで十分です。 |
| トビハゼ属 (小型~大型): 冷凍アカムシ、熱帯魚用フレーク餌、 フリーズドライ系の餌、カーニバル、クリル等 |
自然下では、小型甲殻類やワーム類を食べているため、一般的な熱帯魚用の餌であれば食べるが、餌づかない場合は冷凍アカムシを解凍して与えると良い。同じ餌ばかりだと飽きてくる傾向があるので、いつも与えているもの以外に、他にも食べる餌を見つけておいたほうがいい。 口に入れば生きた魚やエビも食べるので、小型魚と混泳を考えている人は注意されたい。 複数飼育していて一部の魚が餌を食べない場合は、隔離が望ましいが 無理な場合はその個体が隠れているあたりの水中に餌を沈めて与える。ただし、こうしたことが長期間続くと、その個体はストレスで弱りはじめる。 一般流通種:トビハゼ・ミナミトビハゼ・インディアンマッドスキッパー、アフリカンマッドスキッパーなど。アフリカンは店によってジャイアントと表示される場合もあるが、ジャイアントと表示される別種(魚食種 ショーサリ)がいるので間違えないように。 |
| 小型の(最大10cm程度) オオトビハゼ属: トビハゼと同じ。やや魚食魚向きで。 |
上に同じ。 流通種:ベトナムマッドスキッパー(ペリオプタルモドン・セプテムラディアトゥスを指している場合が多いが、流通名は一定していないので この名で売っていても別種の可能性も一応考えて確認する) |
| 大型の(最大30cm近い) オオトビハゼ属: 小赤、メダカ、カーニバル、クリル |
魚食性のマッドスキッパーです。生きた魚を与えるのがてっとりばやいと思いますが、死に餌に餌付かせておいたほうが水も汚れにくく餌の入手・保存が容易なので できるだけ死に餌を食べさせたい所。 流通種:ジャイアントマッドスキッパー(ペリオプタルモドン・ショーサリ ※アフリカンと混同して手から餌を与えないように!噛まれたら血がでます) |